���ܖ�p�[�}�J���`���[�m10���x���|�[�g�i10��22���A23���j
�L�^�ҁF�ؑ��@����q
�u�t�w�F����A�~�����A������A�k�@������i�����������l�j�P�@�G�v��
��i���邭��G�R�v���W�F�N�g�A�̉ԃG�R�v���W�F�N�g�ANPO�n��Â���Ȃǂ�S
�����������j
�Q�X�g�F�����̑f�G�ȉ��l�A���������
�c�O�Ȃ��猇�ȁF�i�i�R����A������������
10��22���i�y�j�P�F�R�O�`
�u�A�[�X�I�[�u�����v
�~�������A�����̍�Ƃ̐�������B
��Ƃ͑傫�������ē��
�P�D�d���ꏬ���̃X�y�[�X�����A���z���
�Q�D�A�[�X�I�[�u������邽�߂̔S�y���ˍ�ƂƓy����
�P�D�A�[�X�I�[�u���̓y��́u��J�i1���F��2500�~�j���g���Ă���B����͉�
�����ŁA�c���������肵�Ă���̂ŁA���̐��g�����Ƃ��x�X�g�ł���B�S�ƃ�
���K�͂䂪��ł��邱�Ƃ�����B�Ȑ��ɂ���ꍇ�͔����x�j�����g���B
�Q�D�܂��̓A�[�X�I�[�u���̓y��ɂ��蔲�������ɂȂ���a�ƊO�a�������M�ŏ�����
��ł����B

�R�D���a�ɍ��킹�āA�u���b�N��ς�ł����B

�S�D���łR�D�̃����K�̎���Ɋۂ��h�[����ɂȂ�悤�Ɍ`����Ă����B




�T�D���Ōł߂���A���ɂʂ炵���V�������h�[���^�̓y�̏�ɂ����Ă����B




�U�D���X�A�~��V�����̏�ɂ͂����Ă����B
�V�D�t�@�[�X�g���[���[�Ƃ��č��ƔS�y���U�F�S�̊����ŁA�������킹�āA�S�y�ƍ�
�����S�ɍ������킳��悤�ɁA���x���Ԃ��Ȃ���A���̂����Ƃ⑫�S�̂ŁA�݂�Ȃ�
���͂��č������킹��B���������������̂����܂����S�y���˂ɂ���āA����ɒe��
���̂���S�y���o���オ��B�o���オ��̖ڈ��͍��̕ӂ肩��ۂ���̔S�y�𗎂Ƃ�
�āA�ڂĂ��Ƒȉ~�`�ɂȂ邭�炢���ڈ��B








�W�D���̔S�y�ŁA��T�����̌����̃u���b�N�����A�U�D�̃��X�A�~�̏�ɔS�y����
����\��t�������B
�X�D�Z�J���h���[���[�̔S�y�ɂ͂��������āA�Ăэ��ƔS�y���U�F�S�̊����ŁA��
�����킹�āA�S�y�ƍ������S�ɍ������킳��悤�ɁA���x���Ԃ��Ȃ���A���̂�����
�⑫�S�̂ŁA�݂�Ȃŋ��͂��č������킹��B
10�D���̔S�y�ŁA�t�@�[�X�g���[���[�̏ォ���T�����u���b�N��̔S�y������
����Ă����B�i�u���b�N�����ɂ��Ă��āA�����������A�y�����u���b�N��
��j
�@







�u���z�`�[���v
�P�D�ꉮ�ƕ��s�ɓy����

�Q�D�����ǂ�ǂ�Ƒg�ݗ��Ă��Ă����B

�i���̍�Ƃɂ́A���ڊւ���Ă��Ȃ��āA�O���猩�Ă��������Ȃ̂ŁA�ڂ�����
�����Ȃ��āA���߂�Ȃ����B�j
�P�X�F�O�O�`
�u�����ł����l�A�k�@������ɂ�鋼���ł��̃f�����X�g���[�V�����v
[�����̂��b]
�����ł����́A�k�C���Y�̐V���ł��B
�@�����͑̂����߂���̂ŁA�������ł���͖̂k�̒n�悪�����B
�@������ǂ�͑̂��₷���̂ŁA�l���ȂǓ�̒n�悪�����B
�@�����ł��͔M�ƕ��Ɏア�B��͗₽���ق����A���������ł����ł���B
�y�����ł��̎菇�z
�P�D���͕��F���Ε��̊������Q�F�W�ŁA�P�������ł̂ŁA���͕����Q�O�O���A����
�����W�O�O�����{�[���ɂ���āA�\���ɂӂ邤�B



�Q�D����3��ɕ����ď����������ē���Ă����B�P�����̕��ɑ��āA���̗ʂ͂T
�O�O���i�������A�V���̏ꍇ�͏��Ȃ߂ŗǂ��B�j
�u���܂킵�v�Ƃ����āA��������āA������S�̂ɒ��J�ɒ��J�ɕ��S�̂ɂ܂킵�Ă�
���B
���́u���܂킵�v�������ł��̒��ŁA��ԑ�ȍH���B
�܂��͔����̂Q�T�O���̐��J�ɕ��ɍ����Ă����B
�Q�D���̌�́A�{���ɂ���ڂ���ړ���Ă����A��15���ʂ����č������킹�Ă����B




�R�D�Ō�̒��߂͌ł��悤���������𐅂ŔG�炵�Ă܂����˂�B
�S�D��������ƍ������킳��A�e�͐������悤�ɂȂ�����A�ۂ��ł߂�B
 �@ �@



�T�D�u�e�B��v�Ƃ����āA�^�����C���O�ɏo���悤�ɁA�e�̉Ԃ̂悤�ɉ�����
��
�Ђ˂肷��B�̂����A�ւ������E�E�E

�U�D�ł����i���������̕����j��̏�ɂ����Ղ�Ƃӂ�A�˖_�̂��Ă����B



�V�D�T���Ԃ��炢�Ȃ���L���B�i��������̂悤�Ɍ����ɂ܂�ۂȌ`�ɐL��
�Ă�����鋼���E�l�A�k����̎�ۂ悳���݂Ȃ���A���̗͉����A�̏d�̂�������
���������܂����B�j
�W�D�������p�̏������炴�炵���˖_�Ɋ����ẮA�L���A�����Ă͐L���Ǝ���
�Ɏl�p���`�ɖ˂��̂��Ă����B



�X�D�S�̂ɋϓ��Ȍ����Ǝl�p���`�ɂȂ�����A�ł����������Ղ�Ƃ����āA�l�p����
�肽����ł����B
�@
 �@ �@





10�D�����ɂ��ꂻ���ȁA������p�̕�i�{����2�`3���~�ʂ��邻�����B�j�ŁA
���Ă͏����������A���Ă͏����������A�Ƃ���������J��Ԃ��āA�ϓ��ɐ���
�����B


11�D�m����\�Ƃ��āA�݂䂫����A������ɒ���B���݂��Ƃł����B
�@
�@

�y�����̂�ŕ��z
�P�D�傫�ڂ̂���ɂ��������āA����������B

�Q�D�܂���2�H�����ς�ς�����B
�R�D�˂���ɂ������Ă�����A10�𐔂��āA�Ԃŏグ��B

�S�D���ł�������Ɛ���āA����ɂ��ꂽ�܂ܕX�ɂ���B


�T�D����ɂ����āA�̂���ӂ肩���A���������܁`���B
�@





�y���z�z
�������ɁA�S�Ǝ�����߂āA���Ԃ������Ē��J�ɂ����Ē������������́u�����v�͍�
���ł����B�{���킳�т�����܂��ō��ŁA���ׂĎ��R�̂��́A����̂��̂���
�ґ𖡂�킹�Ē����܂����B�k����A���肪�Ƃ��������܂����B
���̎���͉��ł��X�s�[�h���Ƒ�ʐ��Y������āA�@�B���H�i������Ă���H�ו���
�����ŋ߁A����̖��ɂ͂ǂ������������Ă��Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��A���������Ă�
�������܂����B�S�����߂Ĉ�������߂č�闿����H�ׂĂ���Ƃ݂�Ȃɂ��ɂ��A��
�݂��ɂ�����荇���A���ӂ��������A�ł��邱�Ƃ��������A�����������Ă�����т�
��������ĉ߂���
�B�Ȃ���E�E�E�ō��̍K���̂ЂƎ��ł����B
�Q�O�F�R�O�`
�y���邭��G�R�v���W�F�N�g�A�̉ԃG�R�v���W�F�N�g�ANPO�n��Â���H�[��ÁA
�P�@�G�v����̂��b�z
���n�̋߂��̑咬�Ƃ����l��3���l�̒��ŁA�n��f�f�}�b�v�A�n��Â��胏�[�N
�V���b�v����Ȃǂ��J�ÁB�����̌������ŃC���L���E�x�[�^�[�Ƃ��Ďd�������A�ǂ�
�������Ƒ̂ł���Ă����̂��A�Ȃǂ������A���H���Ă���B







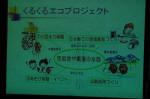







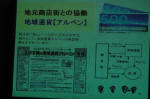
�u���������ڎw�����́v
�P�D�s������̎d�������[�s���ɗ���߂��Ȃ��B
�Q�D�����^�̒n��Â���=�n��̎��������B
�R�D���H�Ɋ�Â��s������̐����E�E�E�s�������ʼnۑ��m��A��̓I��Ă���
�悤�B
���������������ł��邩���l���Ă����B
�d���������[�N�V���b�v����2�̃G�R�v���W�F�N�g�����܂��B
�A�C�f�A���o���Ă����̂͊y�����B�E�E�E������i�荞��ł������Ƃ�����B
�\�Z������E�E�E1�̃v���W�F�N�g��50���~�B��̓I�Ȍ`�Ƃ��č��グ��B
�u��l���z�������H�������Ɂv
�P�D���^���͔��d
�Q�D���Ԃł̒n��Y�i���E�E�E�s�X�n��W���̐��H
�R�D�����ъw�K�A�C�x���g
3�̌��I�Ȑ��͔��d�������E�E��ƁE�_�ƁE�ސE�҂Ȃǂ̂����͂̂��Ƃɏ�����
������ł���B
��͂��x�g�i�����琅�͔��d��A���B�{�́F7��5��~�A�A���R�X�g�F8���~�ŗA
���R�X�g�̂̕��������B
��㐅�́E�E�E�����^���ԁE�E�E���̎O���̈�̓d�C���܂��Ȃ��Ă���Ă���B�@
���S�\�����ϓd��
�u���w�K�v���O�������v
�q�������Ƀ~�j���͔��d���
�u�E�_���̒n��Â���ցv
�s����������s�����ƂցE�E�E�E2004�N10��25�����y��ʏȂ��A������������
���B
�u�s�����Ƃւ̒���v
�P�D�ό��{�݂ւ̃T�[�r�X�T�C�W���O�^�Ɩ��̊J��
�Q�D�ȃG�l�̎x���A�G�R�c�A�[�̗U��
�R�D�s���o���^�v���W�F�N�g�ցA�W���[�d�ւ̋��c
�u�̉ԃv���W�F�N�g�v
��Q�҂̎d������
�H�p���̔p������Ԃ𑖂点��B
�̉Ԗ��͑P�ʃR���X�e���[���𑝂₷�B
�u�n�����X�X�Ƃ̋����A�n��ʉ݁G�A���y���v
�u�����̒n�您�����v
�Y��Ȏ��R�ƒ��a���āE�E�E�E
�P�D�G�l���M�[�̎����E�E�E�C�O�̎����ւ̋ɒ[�Ȉˑ�����߂�B
�Q�D�n��̌��\���������s���̊������n��̖���
�R�D�������܂��d�g�݁E�E�E�⏕���Ɉˑ������A�n��̎��������B


�u�P����̍u���������Ċ��������Ɓv
�ƂĂ���ۂ��������Ƃ́A�P�������ł������낤�Ɨ����オ���Ă�����̂�
�͂Ȃ��A�s���̐����炠�����Ă��Ă������̂��A�݂�Ȃŋ��͂����Č`�ɂ��Ă�����
�Ƃɑ�햡������Ƃ���������Ă������t�B
�����������������Ă��܂������A�����A2002�N��2���ɃI�[�X�g�����A�̃N���X�^
���E�H�[�^�[�Y�A�}���j�[�̒���K�ꂽ�̂ł����A���̎��ɏo������A�s���̐����W
�߂āA�ł���Ƃ��납����A�`�ɂ��āA�R�[�v�����A�n��ʉ݂�����A�s
����s������Ă����Ă���W���E�W���[�_��������v���o���܂����B
�P����̎��g�݂͂��炵���Ǝv���܂����B�P�������ꂽ�{�ɁA�u�Ђ��
�ȁA�������@��A�����ɐ�N���v�ƃT�C�����Ă���ꂽ�̂Ɋ��������Ă�����A�j�[
�`�F�̌��t�Ŗl���ƂĂ��D���Ȍ��t�Ȃ�ł���B�v�Ƃ��b���������̂���ۓI�ł�
���B
����������l��l�����A�Z��ł��钬�ŁA�܂��̓p�[�}�J���`���[�Ŋw���R����
�@����E�E�E�̉��p�ŁA���̒����ώ@����B�Ƃ����Ƃ��납��n�܂�A���̒��ʼn���
�ł���낤���A�L���ɂ��鎑���͉����낤���A����������Ƃ͂ł��Ȃ�����
�����A�������������Ƃ������ɏZ��ł���s���������I�ɍl���āA�A�C�f�A���o��
�����āA�݂�Ȃŋ��͂��āA���̒n��ɂ₳�������g�݁A�l�ɂƂ��Ă����R�ɂƂ�
�Ă��D�������g�݁A���ꂪ���ʓI�ɂ͒n���ɂƂ��Ă��A�F���ɂƂ��Ă����R�̂ł�
���������g�݂ɂȂ��Ă����̂��낤�ȁA�Ɗ����܂����B
�p�[�}�J���`���[�̊w�т͊C�̂悤�ɐ[���đ傫���B���b�L�[�ɂ����N������2�N��
�ł͊w�т���Ȃ����ƂɋC�Â��A�����I��3�N�ڂ����N�����āA���ܖ�ɒʂ����Ƃ�
���S��������҂��ł����B������A���߂����A������A�������A���N����낵
���ˁ[�B
�P�O���Q�Q���@�@�V��F����
�@�@�_�Ǝ��K�i�U�F�R�O�`�W�F�R�O�j
�@�@�O���̑�J�������̂悤�Ɍ����ɐ���ċC�����̗ǂ������}���܂����B

�@�@���T�Ԉȓ��ɏ������~���̂ŁA�Ė�Ŏ����Ȃ��Ă�����̂͂��ׂĎ��n�B��
�����ѓ��͍���J��
�@�~�����̂ŁA�����Ă���ߌ�Ɏ��n�\��B�t���̂͊Ԉ������n�B����ł���Ƃ���
���甲���Ă����Ă���
�@�Ƃ���ɐA����B









�@�@�E�t���̂̈ڐA���@
�@�@�@�@�J���~�����オ�ڐA���₷���A�J���~��Ȃ��ꍇ�́A�P���Ԑ����܂��āA�y
�ɐ������ݍ���ł���
�@�@�@�ڐA����B��ō����������Ĕ����āA�����������Ƃ���ɂP���A����B���܂�
�[���A���Ȃ��B��������
�@�@�@�B�����x�B���͐���ɂ���܂��ȂƎv�����ꏊ��������B
�@�@�E����ǂ����̎�܂��i�����̏m���̂��߂Ɂj
�@�@�@�@�܂��ꏊ������������A���Ԋu�ɂS���܂��B��̔{�̓y�������A�ォ��y��
������i���ɂ킩��Ȃ�
�@�@�@�悤�Ɂj���̎���܂��ꏊ�܂ŁA�Q�O�`�R�O���������B�����ɂ͉肪���A�z
�~����i��������܂��Ƒ傫
�@�@�@���Ȃ肷���Ďキ�Ȃ��Ă��܂��j���N�̂����Ɏ���܂��Ă����ƁA���N�A�P�D
�Q�T�ԑ����H�ׂ���B���N
�@�@�@�t�Ɏx���𗧂āA�Ԉ�������B
�@�@�E�ʂ˂��̕c�����E�E�E�E�����ɋ����A���n�͗��N�̂U������
�@�@�@�@��������A�����L����悤�ɂP�����قǂ̐[���ɒn�ʂ���ɏ��������ł�
�悤�ɐA����B�ォ�瑐��
�@�@�@������B���ԂP�T�����Ԋu
�@�@���n����
�@�@�@�@�@�哤�E�E�E��x�ɉԂ��炢�āA��x�Ɏ��n
�@�@�@�@�@�����E�E�E���ɉԂ��炫�����Ȃ�A�������F�ɂȂ�������n
�@�@�@�@�@�������E�E�E�����~��A�͂�Ă�����n
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�������āA�X�R�b�v�łق�B�P�{�ɂR�`�T�������Ă�
��B�ǖ��H�ׂ���B
�@�@�@�@�@���Ԑ��E�E�E���F���͂�͂��߂�����n�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������������A������ď�Ɏc���Ă�����̂����邩
������Ȃ��̂ŁA�y�̒���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T���Ďc�炸���n
�@�@�@�@�@�ȁ@�@���m�@�@�@�@�@�@�Ȃ������
�@�@�@�@�@�@�@�@���{�i�a�ǁj�@�@�Ȃ��������@�@�J�ɂ�����Ȃ��̂ŁA���{�̋C��
�ɓK���Ă���
�@�E�G�������̐����c��헪�E�E�E���̊Ǘ��A��Ă鎞�̎Q�l�ɂȂ�B
�@�@�@�P�D�A���́uC-R-S�헪�v
�@�@�@�@�@�b�iCompetitive�j�@�@�����^�E�E�E���̐A���Ƃ̋����ɑł����@�@
��F����
�@�@�@�@�@�q�iRuderal�j�@�@�@�@�@�h���ϐ��^�E�E�E�ω��̌����������ŗL���@
�@��F�G��
�@�@�@�@�@�r�iStress tolerant�j�X�g���X�ϐ��^�E�E�E�Ս��Ȋ��X�g���X�i����
�E���ƕs���E�ቷ�j��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@��F���R�A��
�@�@�@�Q�D�G���̐L�ѕ�
�@�@�@�@�@�����^�@�@�厲�ƂȂ�s�i��s�j�������A�c�ɐL�тȂ���}�E�t������
�@�@�@�@�@�قӂ��^�@�@�s�����ւ͂킹�ĐL�т�A���݂��ɋ����A�������Ő���
����A����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȃ����߁A���z�̌����\������B
�@�@�@�@�@���}�^�@�@��s�͎������A���{���̌s����������o���B
�@�@�@�@�@�p���^�@�@�Z���s�E�t����������Q���点�Ċ���A�����_�������ɂ�
���߁A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n�㕔���݂Ƃ��Ă��e���Ȃ��B
�@�@�@�@�@���[�b�g�^�@�ꌹ�FRose �s���Z�������_���Ⴂ�A�n�ʂɉ����ăo���̉�
�т��ɗt���L����B











�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�A�@���i�X�F�R�O�`�P�P�F�P�T�j



�@�@�@�@�����������i�H�ׂĂ����Ԃ����n�̂��́E�E�E���ڂ���A�g�}�g�A������
�@�@�@�@�����������i�H�ׂĂ����Ԃ������n�̂��́E�E�E�Ȃ��A���イ��A�g�E��
���R�V�A����A�s�[�}��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ƃ�
�@�@�@�E���イ��@�@���n��ԁi���F�A�傫���R�O�`�S�O�����j������̂ق��Ɏ킪
����
�@�@�@�@�@�P�D������̕������c�ɔ�����A����X�v�[���Ńr���ɂ����o���B
�@�@�@�@�@�Q�D�ʓ��Ɖʏ`�ƈꏏ�ɒg�����ꏊ�ɂQ�C�R���u���Ĕ��y������BEM�ۂ�
�����Ɣ��y������
�@�@�@�@�@�R�D�{�[���������āA���������Đ���A��������͖��n�Ȃ̂Ŏ̂�
��B
�@�@�@�@�@�S�D�����Ɉڂ��ē����ɔ������Ă�i�V�������Ƃ������Ă��܂��j
�@�@�@�E�g�}�g�@�@
�@�@�@�@�@�P�D����J�b�g���Ď���r���ɂ��ڂ�o��
�@�@�@�@�@�Q�D�ȍ~�͂��イ��Ɠ��l
�@�@�@�E�Y�b�L�[�j�@���{���i��Ȃ����ڂ���j�@���n��ԁi�傫���T�O�`
�U�O�������炢�j
�@�@�@�@�@�P�D���イ��Ɠ����悤����X�v�[���Ńr���ɂ����o���B
�@�@�@�@�@�Q�D�Q��قǐ��Ő���Ċ������i�S�����ɕ����̂Ŏ̂ĂȂ��悤�ɒ��Ӂj
�@�@�@�E���ڂ���@�V���O�Ɏ�����ƒ���������B
�@�@�@�@�@���ڂ���̎���S�����ɕ���
�@�@�@�E�Ȃ��@���n��ԁi���F�j
�@�@�@�@�@�P�D������̕����c�����ɐ�A���̒��Ŏ�����o���B
�@�@�@�@�@�Q�D�Q�C�R���A�����ɂ��ĂĔ��y������B
�@�@�@�E�s�[�}���A�Ƃ����炵�@�@���n��ԁi�ԐF�j
�@�@�@�@�@������o���Ă��̂܂܊������B
�@�@�@�E������
�@�@�@�@�@�P�D���₩��͂����A�悭�����ɂ��Ă�B
�@�@�@�@�@�Q�D�������Ȃ��悤�Ɋ��S�ɂ��킩���Ă��炵�܂��B�i�r���ɓ�����
�������Ȃ��j
�@�@�@�E���^�X
�@�@�@�@�@�͂��܂łق����Ă����A�J���J���ɂȂ����Ԃ̒����������o���B
�@�@��̓r����J���ɓ���āA���x�E���x�̒Ⴂ�ꏊ�ŕۑ�����B�①�ɂ��œK
�@�@���R�_�@�Z���^�[�ł́A���n������̂܂ܕ��u���āA��������ƂȂ�����ォ
��y����������B
�@�@���y�������������藦�������i�V�|�W���j
�@�@
�@�@�u���ƍ̎�����悤�v�i�v�����g�̕⑫�j
�@�@�@�e�P��q�@�@�L����`�łQ�̕i��̗ǂ������������p���ł���B�Ȋw�엿��
�g�p��O���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ă���B�i�������肵�Ă���B�e�Q�͗�`�ɂȂ��Ă���
���̂ŁA���N�w�����Ȃ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ȃ��悤�ȃV�X�e���ɂȂ��Ă���B���@��c��Ђ̐헪
�@�@�@���ƍ̎�̗��_�@�@���N�����y�n�ɐA����ƁA�炿�₷���i��i���̐�����
���������́j��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ��Ă����B�����w��ł����B
�@�@�@�ǂ̂悤�Ȃ��̂�I�Ԃ��@��Ԍ��N�Ȃ��́A�傫���͊W�Ȃ����玞����ڂ�
�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Ԃ������̂͐H�ׂ��Ɏc���Ă����B























































�B�@���R�̃p�^�[���ƃp�[�}�J���`���[�i�P�P�F�P�T�`
�@�@
�@�@�@�X���C�h�ŐA�����̃f�U�C�����Љ�
�@�@�@�@�@�����A�����̑��A���A�݂���A����̂��傤�����A�g�}�g�A�X�^�[�v
���[�c�A�ԂƖI
�@�@�@�@�@�g�E�����R�V�A�_�C�������h�x�m�A�Ȃ��E�E�E�E
�@�@�@�����\�ȃ��C�t�X�^�C���̎肪���肪�A���R�����z�̎d�g�݂̒��ɂ���
�̂ŁA
�@�@�@���R���ώ@���A���̎d�g�݂𗝉�����A��炵�̒��ɂ��̗�������܂����
����邱�Ƃ�
�@�@�@�ł���B




�@�@�@�E���R�̃f�U�C�����[�N����w�Ԃ���
�@�@�@�@�P�D���@�\�������ˏ�
�@�@�@�@�@�@�����J�^�`�ł����Ă��A�ɉ����ĈقȂ�@�\��
�@�@�@�@�@�@��F�����̗t�@�|�@���𗧑̓I�ɂƂ炦��
�@�@�@�@�@�@�@�@�L�N�̉ԁ@�|�@�������邱�Ƃ𒎂����ɃA�s�[��
�@�@�@�@�@�@�@�@�N���̑��@�|�@���̏�Őg�̂�����
�@�@�@�@�Q�D���ʐ����ނ�j�^
�@�@�@�@�@�@�قȂ鐶�����ł����Ă��A�����@�\�����߂�Ɠ����f�U�C���ɍs������
�@�@�@�@�@�@��F���܂��邽�߂̃f�U�C��
�@�@�@�@�@�@�@�@�I�I�I�i���~�A�A���`�k�X�r�g�n�M�A�}���R�K�l
�@�@�@�@�R�D���l�������[�@
�@�@�@�@�@�@���߂�@�\�͋��ʂ��Ă��Ă��A�ɉ����ĈقȂ�f�U�C�����̗p
�@�@�@�@�@�@��F�V�_�̐V��i�Q����j�������R�[�h���������h����
�@�@�@�@�@�@�@�@�����i�ʎ��̒��ɉ��S���̖���̔����킪�[�܂��Ă���j���L���r
�l�b�g
�@�@�@�@�@�@�@�@�g�E�����R�V�̎��i�H������L�����p�j���~�c�o�`�̑�
�@�@�@�E���R�̃p�^�[���ƃG�l���M�[�̗���
�@�@�@�@�P�D�X�p�C�����@�@�G�l���M�[�����S�Ɍ������ďW�����鎞�ɂ����Ƃ�����
�I
�@�@�@�@�@�@�@�X�p�C�����K�[�f���E�E�E���̓I�ɂ��邱�ƂŁA�����E���A�E���E��
������B
�@�@�@�@�Q�D�L�[�z�[���@�@�L�[�z�[�������邱�ƂŃf�l���M�[����������������
���܂��₷���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���܂��܂Ȃ��̂��^��Ă��邱�Ƃ�����
�@�@�@�@�R�D�g�^
�@�@�@�@�S�D�G�b�W���ʁ@�@�X�ѓ����E�E���ׂ����₩�A���������܂����Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�щ����E�E�E�E�C���̏㏸�E�����ȂNJ�����������
��
�@�@�@�E���R�ώ@�̃|�C���g
�@�@�@�@�@Slow down �@�������
Get down�@�@���_��Ⴍ
Silence�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@���Ȃ��G�l���M�[�ʼn��K�ɉ߂����q���g������B
�@�@�@�@�@�@���R�͂��낢�닳���Ă����B
�C�@�A�[�X�I�[�u���쐬�i�P�R�F�R�O�`
�@�@�@�I�[�u���̂R�������C���[�`�[���ƁA�܂��u����`�[���ɕ������ƊJ�n
�@�@�@�R�������C���[�`�[��
�@�@�@�f�U�C���̓J�G���̊�Ɍ���B
�@�@�@����Ɠ����v�̂Ńf�U�C���p�̓D������B�����������肵�āA�S�y�ƍ��̔z
�����������
�@�@����ǁA���˂��˂���͎̂q���̂���ɂ悭������D�V�т݂����ŁA�Ƃ��Ă��y
���������B
�@�@�@�����̃f�U�C���̓J�G���̊�B�ł��B�݂�Ȃ��ꂼ��D������ɍD���Ȍ`����
��������
�@�@�̂ŁA�o���オ���Ă݂�ƁA�Ƃ��Ă��f�G�ȃf�U�C���ɂȂ��Ă܂������Č�
�肵�Ȃ������̂��A
�@�@�悩�����悤�ł��B







 
























�P�O���Q�S��
���̍������o���ăr�[�ʂ��O���ɖ��ߍ��݂܂����B



 |