『自然と調和したこれからの ライフスタイルを考える』
講師:デビッド・ホルムグレン氏 通訳:リック・タナカ
リポート 梅崎靖志
○パーマカルチャーとは
パーマカルチャーは持続可能な生活、そして持続可能な土地利用をデザインするための体系です。つまり、パーマカルチャーは自然と調和した暮らしのデザインであるといってもよいでしょう。もともとは、「パーマネント(永続的な)」と「アグリカルチャー(農業)」「カルチャー(文化)」をあわせて「パーマカルチャー」という造語が作られました。
パーマカルチャーは暮らし全体を扱うことから、対象となる分野は多岐にわたります。つまり、土地や自然を利用した農業、林業、建築といった分野から、教育や文化、健康、経済、地域社会のあり方にまで及びます。
また、パーマカルチャーは、持続可能な社会を作るために、現在のエネルギー消費の多い社会から、いかにエネルギー消費の少ない社会へと向かい、持続可能な社会を見つけていくか、という課題に対する取り組みであるといえます。
自然が持つ限界を見極め、自然の豊かさを暮らしに取り入れることを通じて、自然の中に自分たちの暮らしの場所をどのように取り戻していくかという意味で、パーマカルチャーは、自分がいる「今、ここから」始めることのできるものなのです。
○パーマカルチャーの歴史
パーマカルチャーは、タスマニア大学の教員だったビル・モリソンとその学生デビッド・ホルムグレンがともに作り上げた永続的なライフスタイルの枠組みです。世界的な歴史の流れの中で位置づけると、60年代後半から70年代にかけて盛り上がった環境への関心の高まりから生まれてきた運動のうちの一つであるといえます。
二人の共著で「パーマカルチャー1」が1978年に出版されて、パーマカルチャーの原理が始めて紹介されました。
その後、ビル・モリソンはパーマカルチャーを広めるための活動を精力的に行ったことにより、世界中に広まりました。
デビッド・ホルムグレンは、パーマカルチャーの具体的な事例を作るために、自然と人間が再び結びつくための技術を獲得しようと、30年の実践を積んできました。できるだけ物を持たない簡素な暮らしの中で、パーマカルチャーの要素である庭いじり(ガーデニング)や農業、建築の技術、森林に関する技術を学び、実践を積んできて、その成果をまとめた本を2002年に出版しています。この著書では、実践を踏まえて理論に立ち返り、理論の再提示を目指し、パーマカルチャーの12のデザイン論を論及しています。
「Permaculture / Principles & Pathways Beyond Sustainability」
○食べ物の自給
パーマカルチャーでは、自宅での野菜や果物を作ることを特に奨励しています。これは、庭で食べ物を作るということが、一番持続可能な農法であることによります。
自宅の庭で、新鮮な野菜や果物を育てることは、フードマイル(作られた場所から消費される場所までの距離)を短くすることになります。また、食べ終わったあとの食べかすもその場所で堆肥化することで、循環させることができます。地産地消(土地で作った物をその土地で消費する)を実践することが、余分なエネルギーの消費を抑えることにつながります。
食べ物を自宅で作ることのもう一つの意味は、庭いじりを通じて自然と再び関係を持つことができるということにあります。自然の中へ出かけて行き、それを見て楽しむだけではなく、自然と一緒になって暮らしていくことに大きな意味があります。
○多様性を大切にする
パーマカルチャーで重要な概念の一つに、生態系の多様性を保つということがあります。作る野菜も単一の作物ではなく、多様な作物を作ることを奨励しています。そして、パーマカルチャーでは、一年生の野菜よりも多年生の作物を利用することに重点を置いています。樹木の利用を推奨していることもパーマカルチャーの特徴です。樹木は、野菜に比べて土の中の栄養、水、日光を利用する力が優れています。
生態系の多様さの重要性という視点で考えると、将来の生産にとって一番大切なこととして、作物のタネの確保があげられます。現在、タネは大手の種苗会社の手に握られつつあります。こうしたことへの対抗策として、自分たちの手で種類を保存していこうという動きがあります。
パーマカルチャーでは、作物の中でも伝統的に何百年も栽培されてきた種を守ることを推奨しています。こうした種は、生産力も高く、耐病性もあるからです。今、こうした優れた品種が失われつつあります。
●食べ物の保存について
パーマカルチャーでは、食べるものやそのほか人間に必要なものの生産を重要視する一方で、生産したものをどのように消費するかということにも気を配ります。旬の食べ物を食べるということは自分の身体にとっていいだけでなく、地球の環境にもいいといえます。また、たくさん取れた旬の作物をどう保存するかということもパーマカルチャーでは重要視しています。
昔ながらの方法であまりエネルギーを消費しないで、たくさん取れた旬のものを保存する方法はいろいろあります。たくさんできたトマトを使ったパスタソース、たくさん取れた果物の瓶詰め(真空保存)、それからジャムなどに加工することで、旬の時期にたくさん取れた収穫物を保存することができます。そして、こうした知恵を子どもに伝えるのは、家庭でやるのが一番いいといえます。
○地力を回復させることは食物生産の基礎
地力を保ち回復させるための方法としてパーマカルチャーがすすめるものには、堆肥場の利用や緑肥植物の栽培などがあります。
パーマカルチャーでは、こうした昔ながらの方法だけでなく、新しい方法も取り入れています。その一つはミミズを使って生ゴミを処理するミミズコンポストです。都市部での台所から出る生ゴミを処理する方法として世界で広く使われています。
また、新聞やダンボールを使ったシートマルチは、パーマカルチャーが盛んにすすめた方法です。新聞やダンボールを利用したシートマルチは、新しく菜園を作るときに有効な方法で、雑草が生えているところに使います。光をさえぎり、雑草を抑える効果があり、マルチとして使った新聞紙やダンボールは、時間とともに分解して土にかえっていきます。シートマルチは、ゴミとして捨てられる手元の資源をいかに有効に使うか、という一つのやり方です。パーマカルチャーでは、今ある資源を再利用することを考えるのです。
●樹木の利用
パーマカルチャーでは、木の重要性を説いています。食べ物に関しても一年草に頼るのではなく、多年生の木を食べ物の重要な供給源と見ています。例えば、ピスタチオの実の生産は、小麦の生産に比べて環境にやさしいといえます。特に、オーストラリアのように乾燥した場所では、小麦よりずっと環境への負荷が小さくなります。もともと中近東あたりが原産ですが、オーストラリアの南部でも生産されています。
また、日本でも(農家の庭先に、カキやウメ等の有用植物が植栽されているように)、昔から米や麦の生産を補うために木になる果物や木の実が利用されています。
○動物を積極的に取り込んだシステム
・ニワトリを利用した例
動物を利用した方法としては、チキントラクター(ニワトリを使ったトラクター)があります。作物の収穫が終わったあとにニワトリを入れると、ニワトリはエサを探すために土をほじくり返し、畑をきれいにしてくれます。ただし、チキントラクターを行う際には、作物が育っている場所と収穫が終わっている場所を分けて作物を育てている畑にニワトリが入ってこないようにする必要があります。
日本では、動物を利用した方法にアイガモ農法があります。この方法は、アイガモが雑草を食べて米の生育を助けるだけでなく、アイガモも一緒に生育して、秋には米とアイガモの両方が収穫できる合理的なシステムだといえます。
・ブタを利用した例
ブタを竹林の中で放牧するやり方があります。タケノコをブタが食べることで、竹林が広がることを防ぎ、ブタも育ちます。また、土地のやせたオーストラリアでは、豚のフンが大切な肥料になるとともに、竹林内でブタを飼うことでブタの日焼けを防ぐ効果もあります。
また、竹林で放牧する際には電柵も使っています。このように、パーマカルチャーではエネルギーのかからないローテクを推奨すると同時に、新しい技術を効果的に取り入れていくという視点も大切にしています。
●燃料としての薪の利用
ここまでは人間の食べ物の生産と消費を基本にご紹介してきましたが、その他のものも自然の中から得ることができます。パーマカルチャーではなるべく自然に近い形での森林経営を目指し、そこから採れる木を、例えば「用材」として利用します。植林されて工場のような状態で育てられる木と異なり、なるべく自然の中で育てながら、自然の恩恵にあずかるというのがパーマカルチャーのやり方・考え方です。
オーストラリアのフライヤーズ・フォレストというエコビレッジで育つのは、かなり成長の遅いユーカリの木です。ここで採れるユーカリの木は、いわゆる堅木で非常に重く、燃料や工業用の用材などに使われてきました。家の手前にダムがあり、その手前に間引きされた林があります。間引きというのは、育ちの悪い木、曲がった木などを少しずつ伐採して燃料や用材として利用していくことで、残った木が太く高く育つようにすることです。こういう間引き作業を続けて残った木が建築用材として使えるようになるまでに約80年かかります。このような森林経営のやり方は、経済的に割が合わないといわれます。しかし、将来の価値、環境への負荷等を考えるとこうした方法のほうがずっと価値が高いと考えられます。
森林経営から生まれてくる自然の恵みは、まず燃料として利用されます。薪というのは燃料の中でも持続可能であり、燃焼効率もいいものです。デビッド・ホルムグレンの家では、薪を利用して調理したり、お湯を沸かしたりしています。その結果、一年間で使う薪の量は5トンくらいになります。台所には小さなガスレンジがありますが、ガスの使用量は一年間で小さなガスボンベひとつだといいます。また、メルボルン市内で作られるパンのほとんどが、ガスを使ったオーブンで焼いていますが、シリーズという都市農園にあるパン屋さんは、市内で得られる薪で天然酵母のパンを焼いています。日本でいま再び脚光を浴びている炭焼きも、森林と関連して持続可能な資源を使っていくという、一つの大きな取り組みだといえます。
●建築材料としての自然素材の利用
パーマカルチャーでは、樹木を含めた生物素材の利用に関心を持っている一方で、自然の中にたくさんある生物以外の材料(非生物素材)の使用を勧めています。
オーストラリアのフライヤーズ・フォレストには、コンクリートの代わりに石組みを使った壁面があります。デビッド・ホルムグレンが、オーストラリアで「これは優れた石の使い方だ」と紹介していたところ、日本でずっと優れた石の組み方を見てからは、(組み方が素人仕事なので)非常に貧弱な例だと感じたそうです。彼は、日本では伝統的に石などの素材をうまく利用しているのに感心する一方で、コンクリートが使われすぎているのではないかと衝撃を受けました。パーマカルチャーがコンクリートを批判するのは、見栄えが悪いということではなく、コンクリートの生産にはたくさんのエネルギーが必要で、それが再生不可能な材料であるという点によります。もちろん、今あるものは利用しなければなりませんが、将来私たちの子孫がこれを維持したり、修復するのが難しくなると考えられます。これは日本だけの話ではありません。先進国の中では、今あるインフラを維持するためにかかる維持費の高さが問題となっています。
建築や構造物には、コンクリートの代わりに石や、日干し煉瓦といった自然の材料を利用することができます。石や日干し煉瓦は、熱をためる蓄熱体としての利用ができます。また、大きさを自由に調整することのできる日干し煉瓦は、耐加重性のある建築材料としても利用できます。
●エネルギーの効果的な活用
パーマカルチャーでは、なるべくエネルギー消費の少ない昔ながらの方法を奨励していますが、土木工事のように石油、化石燃料を使うこともそれが創造的であるなら奨励する場合もあります。
例えば、デビッド・ホルムグレンが自分の家を1986年に作ったときには、ダム(ため池)や家を建てる場所の整地に重機を利用しています。
●自然負荷の小さな家作りの考え方
パーマカルチャーは自然を相手にする一方、人工的なものにも関心があります。例えば、日干し煉瓦を使って家を作ることができます。日干し煉瓦を作る材料は、オーストラリアのように土地がやせたところにはたくさんあります。しかし、日本では土が肥えすぎていて、日干し煉瓦の材料になるような土はあまりないようです。
自然の中から得られた材料で家を作る一方で、家のデザインも大切です。デビッド・ホルムグレンの家は、パッシブソーラーでデザインされています。そして、冬の間の暖房は90%が太陽のエネルギーでまかなわれています。
○水の収穫と浄化
パーマカルチャーでは、水の収穫と使用した水の浄化処理ということも重要なポイントとなります。
屋根に降った雨をタンクにためて使うこと自体は、オーストラリアという乾燥した環境の伝統的に行われてきたアイデアです。
パーマカルチャーでオーストラリアの乾燥した環境で作物を育てるのに雨水を利用するという話をすると、「そんなのずっと前からしていたじゃない」、ということになります。もともとオーストラリアは雨水を利用する伝統のある土地ですが、ここ30−40年の間にほとんどの人が水道の水を使って暮らすようになっています。そのため、オーストラリアの伝統的な手法が身近でなくなり、パーマカルチャーを通して人々が改めて見直している、という側面もあります。
オーストラリアで屋根の水を集めるということは新しいアイデアではありませんが、使用した水をヨシなどの植物を使って浄化するというのは新しいアイデアです。
※日本では、台所からの排水をためて鯉を飼ったり、レンコンを作ったりしていました。こうした手法は、使った水をきれいにするための伝統的な手法であるといえます。
●自然と調和したこれからの暮らしと、パーマカルチャーの果たす役割
パーマカルチャーとは、持続可能な生き方、持続可能な土地の利用方法をデザインするシステムです。そして、それを実施する人、活動家、団体、それを含めた国際的な活動であり、草の根の運動です。その過程で、私たちの居場所を自然の中に再び取り戻すことを目指しています。パーマカルチャーは、自然を観察することによって見つけられた倫理的な原理、デザイン原理から始まります。そして、自然の中から見つけた原理を、自然の中で応用していくことになります。具体的には、「庭いじり、農業、動物の飼育、林業など」に活かすことができます。同じ原理が、「人が作った建物・人間が作る環境」「どのような道具や技術を使うか」という領域にも適用が可能です。この三つの領域は、パーマカルチャーが実践的に使える領域だと言っていいかもしれません。ところが、持続可能な社会を作るには、このほかに四つの領域にパーマカルチャーを応用していくことが必要です。
まずは、「文化と教育の仕組み」を変えていく必要があります。二番目として、「私たち自身の身体と心の健康」も持続可能な社会には欠かせません。三番目には、「金融・経済システム」です。これはもともと人間の道具だったはずが、今では人間をコントロールするようになったと感じている方も多いと思います。四番目は、「土地の所有形態と社会の中での意思決定のされ方」も持続可能な社会では新しい形が必要になります。
これからパーマカルチャーの原理が適用されなければならない分野で、すでにどんなことが行われているのか実例をご紹介します。
・文化と教育の仕組み
私たちがまず打ち砕かなければならないものは、「学ぶ」ということが専門家に聞いたり、本を読んだりすることだという固定観念です。小さな子どもを自然の中に連れ出し、自然を体験させることでも学ぶことはできます。つまり、自然を直接観察し、自然と関わることによって学びを得ることができるのです。
いわゆる普通の教育の場でも、新しい教え方が必要になってくると思います。例えば、パーマカルチャーの教室で行われている新しい教育の仕方があります。この方法では、ため池をどこに作ったらいいかを学ぶのに、専門家や本から学ぶのではなく、実際に水を流して学びます。
そしてもう一つ重要なのが、伝統的な文化や先住民族の文化の再評価です。例えば30年前に、ニュージーランドの先住民族マオリの言葉はほとんど絶滅状態でした。しかし、今年の初めにデビッド・ホルムグレンが講演したニュージーランドのエコショーでは、歓迎セレモニーのあと、様々な催しのほとんどに通訳が必要だったといいます。というのは、こうした催しがマオリの言葉で行われたからです。
・土地の所有形態と社会の中での意思決定のされ方
共同農園や都市農園は、オーストラリアの社会に広がりつつあります。ほとんどが公共の公有地を使って行われていますが、そこに様々な人が集まり、自分たちの食べるものを生産する、そしてそれが環境を共有する場になるという効果を生み出しています。オーストラリアの都市農園では、ニワトリを使ったり、動物と植物を一緒に組み合わせるということが行われています。持続可能な社会では、新しい形態による土地共有の方法も必要になってきます。エコビレッジやデンマーク生まれのコ・ハウジング(プライバシーを尊重しつつ共同空間をもつ共同居住型住居)という考え方で土地を共有する方法が、オーストラリアで盛んになっています。また、ニュージーランドのアース・ソングという場所(集落)のデザインでは、最初から住民が加わり、それぞれの家の建て方や場所を決めていく(集落をデザインしていく)という、特徴的な方法が取られています。そして、家自体はコンパクトな設計なので、余った土地で共同農園を行うことができます。
・金融・経済システム
持続可能な社会では、それにふさわしい経済の方法、つまり、それぞれの人がものを交換する方法が必要になります。地域通貨を使っていくことで、すべてを現金に頼った生活から、それ以外の取引の方法も存在するという状況を作り出すことができます。日本でも地域通貨の必要性が叫ばれ、実際に取り組みも始まっています。
パーマカルチャーが適用されている領域
・土地と自然の利用:農業・林業など
・人工環境:建築など
・道具と技術
これからパーマカルチャーが適用されるべき領域
・文化・教育:持続可能な社会のための教育など
・身体と心の健康:部分ではなく身体全体をとらえるホリスティックな考え方
・金融・経済システム:小規模な地域に根ざした経済活動(地域通貨など)
・土地所有・地域社会のあり方:土地の利用法を含むコミュニティの運営
●おわりに
パーマカルチャーというのは、ここでご紹介した七つの領域をつむぐものです。全体を見渡すと、すごく複雑で大きいために、とても手に負えないのではないかという気がするかもしれません。しかし、パーマカルチャー実践の出発点は、一人ひとりの個人にあります。個人が自分の暮らしを変え、それが家族、友人、地域社会という形で広がっていきます。こうした広がりが、より良い社会を作るきっかけとなります。
このように、具体的な取組みの中から、より良い持続可能な社会のあり方を見つけていくことが、パーマカルチャーの目的であるといえます。
※この原稿は、2004.6.6に開催された NPO法人パーマカルチャー・センタ・ジャパン設立記念講演会、および2004.6.13柏崎・夢の森公園 環境学校セミナー特別講演会におけるデビッド・ホルムグレン氏の講演をもとにまとめました。
●デビッド・ホルムグレン氏 プロフィール
デビッド・ホルムグレンは、タスマニアの自然に魅せられ、ホバーとの独創的な環境デザイン/設計学校に入学し、恩師ビル・モリソンと共同作業の上にパーマカルチャーの理論を構築した。ホルムグレンは「パーマカルチャー1」の若き共著者としての脚光をさけ、自足生活のための実際的な技術、デザインを磨き発展させていった。
設計/デザイン・コンサルタントの活動を通し、南東オーストラリアの寒冷気候での経験が豊富で、自宅近辺の生態には特に詳しい。オーストラリアでパーマカルチャーが最もよく具現された展示サイトといわれるヘップバーン・スプリングの自宅を拠点に活動を続け、過去7年間、フライヤーズ・フォレスト・エコビレッジの開発を推進してきた。国際的なパーマカルチャー運動の中で、ホルムグレンは現実的なプロジェクトを通じて、パーマカルチャーの考えを広めてきた功績で尊敬されている。個人的な経験を通し、持続可能な生活スタイルは十分可能なもので、消費漬け社会への強力な対抗策だと教える。
近年の著書「Permaculture / Principles & Pathways Beyond Sustainability」は、サステナビリティ社会は長期的な未来であるとし、そこに至るための今日的な暮らし、文化のあり方について、パーマカルチャーの12のデザイン論を論及している。
シャロムでの歓迎会
長野県波田の自然農法国際研究開発センターにて
ヘップバーン・スプリングの自宅

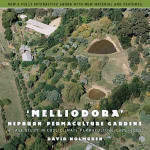

_small.jpg)